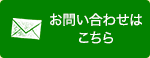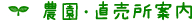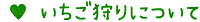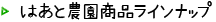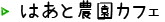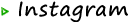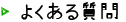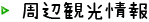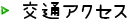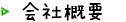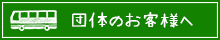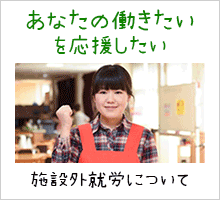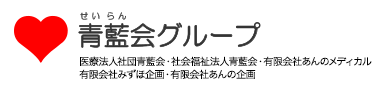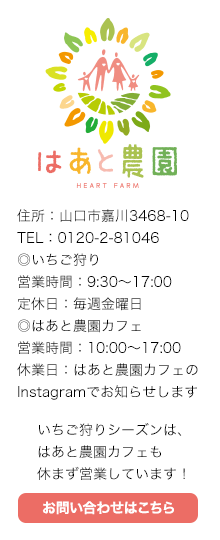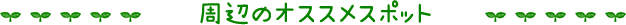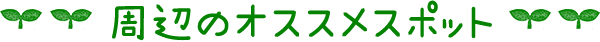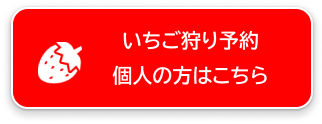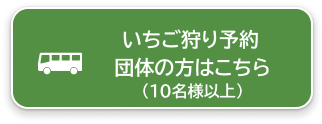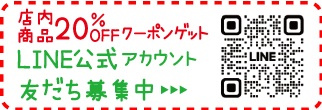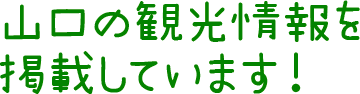
はあと農園から比較的近い観光スポットの情報をまとめました!
はあと農園でいちごを堪能した後は、温泉や自然を楽しむのもよし、歴史に触れるもよし、山口の魅力を体験してください!

山口市にある有名な温泉地です! 湯田温泉はアルカリ性単純温泉で、肌によく馴染むやわらかい湯が特徴です。
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、ぢ疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進に効能があるため、昔から多くの人々に親しまれ、そして愛されてきました。
しかし、一番の特徴は豊富な湯量、1日になんと2,000トンもの天然温泉が湧き出ているのです。

長門峡は山口県を代表する渓谷で、国指定の名勝地です。
奇岩や滝、深淵など、日本画のように美しい奇勝として知られています。
サクラ・フジ・コブシなどの花が咲く「春」、新緑が美しい「夏」、山々が赤く染まる紅葉の「秋」、雄大な雪景色に出会える「冬」と、四季を通じて楽しむことができます。

(ふれあいぱーくおおはらこ)
澄んだ湖で知られる大原湖畔に平成10年4月にオープンしました。
ケビン5棟、オートキャンプサイト23サイト、一般キャンプサイト21サイトの規模を持ち、キャンプ用具の他カヌー、フィッシングセット、マウンテンバイク等レンタル用品も充実しています。
大原湖には毎年ニジマスを放流しており、釣りを楽しむこともできます。また、「ふれあいパーク大原湖」を含む約3,700ヘクタールは「森林セラピー基地」として認定を受けています。

(こくほう るりこうじごじゅうのとう)
大内氏前期全盛の頃、25代大内義弘は現在の香山公園に、石屏子介禅師を迎え香積寺を建立しました。
義弘は応永6年(1399年)足利義満と泉州で戦い戦死。26代弟・盛見は兄の菩提を弔うため、香積寺に五重塔を造営中、九州の少貳勢と戦って戦死。五重塔はその後、嘉吉2年(1442年)頃落慶しました。
それからしばらくの時を経た関ヶ原の合戦の後、毛利輝元が萩入りし、香積寺を萩に引寺。跡地に仁保から瑠璃光寺を移築しました。これが今日の姿です

庭園は、今から約500年前、妙喜寺の時代に、大内政弘が別荘として、画僧雪舟に築庭させたものと伝えられ、現在国の史跡及び名勝に指定されています。
庭園は本堂の北面にあり、内庭は約30アールの広さで、東、西、北の三方が山林となっています。近年この山林も指定地域に含まれました。庭に使用されている石材はこの近くの山から運搬したものと言われる輝岩です。
庭は北側に滝を掛け、中央には無染池(心字池)を設け、その周囲には庭石を豊かに配しています。石は室町時代の特色となっている立石が多く使用されています。庭の上方に小高い丘陵がありそこに四明池、弁天池の水源があります。

町屋づくりの建物が建ち並ぶ竪小路の傍らに朱色の大鳥居が印象的な場所があります。
本社は大内弘世が応安2年(1369年)に京都から勧請したものです。はじめは社殿は竪小路に建立されましたが、更に水の上に社地がかえられました。その後、永正16年(1519年)に大内義興が大神宮を高峯山麓に建立したとき、本社もその地に移し、社殿を新築しているそうです。